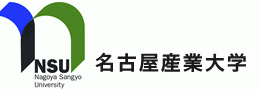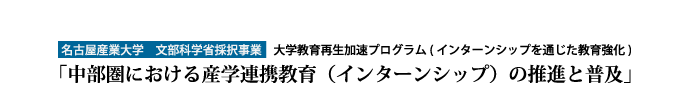働くということを語るとき、対価としての賃金(給料)を抜きにして考えることはできない。
私が5年前まで働いていたシリコンバレーのIT企業の日本法人では、昼も夜もないような生活であった。昼間は営業部門との打ち合わせや販売パートナーとの交渉、夜は時差の関係で米国本社とTV会議や電話会議、オフィスは24時間空いていた。給料は良かったが、3人分くらいの仕事を1人でこなさねばならなかった。給料を半分にしてもう1人雇ったらと考えるところだが、英語が出来て製品マーケティングのスキルがある人材はそう簡単にはいない。他の外資系IT企業からも高給で引き抜きの話しがくる。いうなれば、競争原理による労働の付加価値は、対価としての賃金で評価される世界である。
日本では若い人たちに仕事がないといわれて久しい。不況による就職難が叫ばれているが、就職難は下位30%の学生の問題である。上位30%の価値の高い学生はどこの企業からも引っ張り凧である。金融・コンサル・大手メーカーからいくつも内定をもらい、どこにしようかと迷う学生は多くいる。「初任給はここがいいけど、生涯賃金ではあそこかなあ」などという会話が飛び交う。彼らは、留学経験や英語・中国語・ドイツ語・フランス語など語学力、難関資格を武器に業に入る前から既に企業戦士である。
結局、どの時代、どこの世界に行っても競争原理による付加価値の評価はあるのである。
加藤和彦