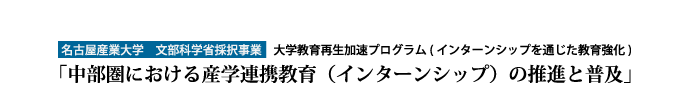成田暢彦
働く動機は、年齢や自らの置かれた状況により異なるが、生活、物的欲求など様々である。私自身の働く動機も、年を経るに従って変化してきた。その変化を追ってみたい。
<対価>
若いときのアルバイトの動機は、物的な欲求であり、例えば自分が満足できる自動車を手に入れたいと切望していた。しかし、単に金を追求していたわけではなく、仕事後には「客がこの内容で満足するのか? 自分が客だったら満足したのか?」を何となく考えるようになった。企業では、既に20年以上前から成果主義が唱われ、それは昇級やボーナスに反映されているが、時間的にも精神的にも余裕が無かった時期には、成果主義など気にせず、黙々と業務を続けてきた。しかし、いつからか「自分が得た給与(対価)に見合う仕事の結果であったか?」をその仕事が終わりかける時点で振り返り、仕上げる段階で見直すよう心がけている。ここで、対価とは自分の仕事の成果に対する報酬であり、自分の時間を損失したことによる報酬(時給)ではない。今でも、仕事を担当する時の対価を考える習慣は抜けない。
<働きがい>
企業に就職したての頃は、上司から指示された仕事を、注意を受けながらも黙々と担当したが、3年もすると自分でしか説明できないような内容の仕事もできるようになってきた。この業務を具現化するため、関係部門との調整が必要となり、徐々に自分の業務内容が広がり、自信がついてきた。今思えば、自分のなかで初めて働く意味(働きがい)を認識した。しかし、仕事がどんどん増え、コスト管理の課題などが降りかかってきた時期でもあった。その後、会社内の種々の部門の業務を経て、自分しかできない仕事、言い換えれば、業務命令で自分が責任を持つ仕事を担当することで、自分なりの仕事の進め方を学んできた。大企業では自分の業務が会社の歯車の一つでしかないと言われる場合もあるが、歯車も一つ欠ければ機械が動かなくなると自負を持った。しかし、課長になり「自分の本当の仕事/会社への寄与とは?」を考えたとき、その考え方は自分が所属した企業の考え方に染まっていることに気づいた。これは会社の仕事により自分が成長したことの証であるが、一方で新しい仕事への興味も湧き出してきた。当時は、バブル景気が終わり、新たな仕事を開拓することが期待されていたため、45歳で再び新たな内容の業務へのチャレンジを開始したが、これが大学教員への路のスタートであった。
自分自身で仕事を創出することは、企業に入社して直ぐにできるわけではない。企業に育ててもらって、“自ら”働くことができる。そのために、辛抱が必要な時期があり、仕事の意味が理解できなくても、仕事に傾注し堪え忍ぶことが必要ではないだろうか。